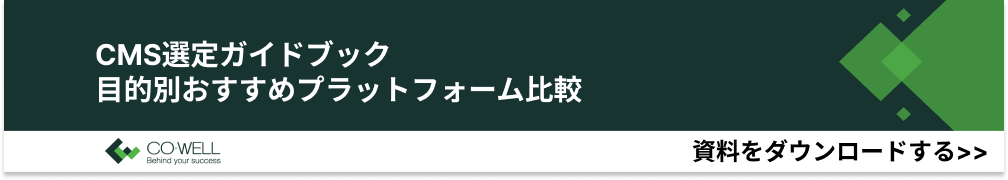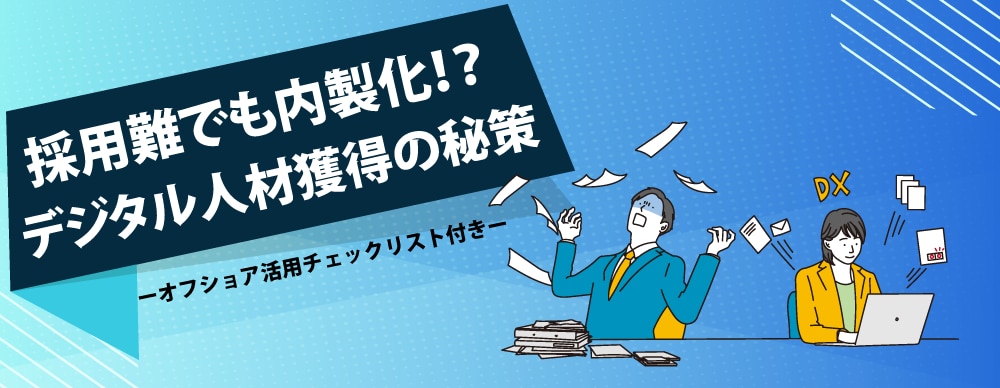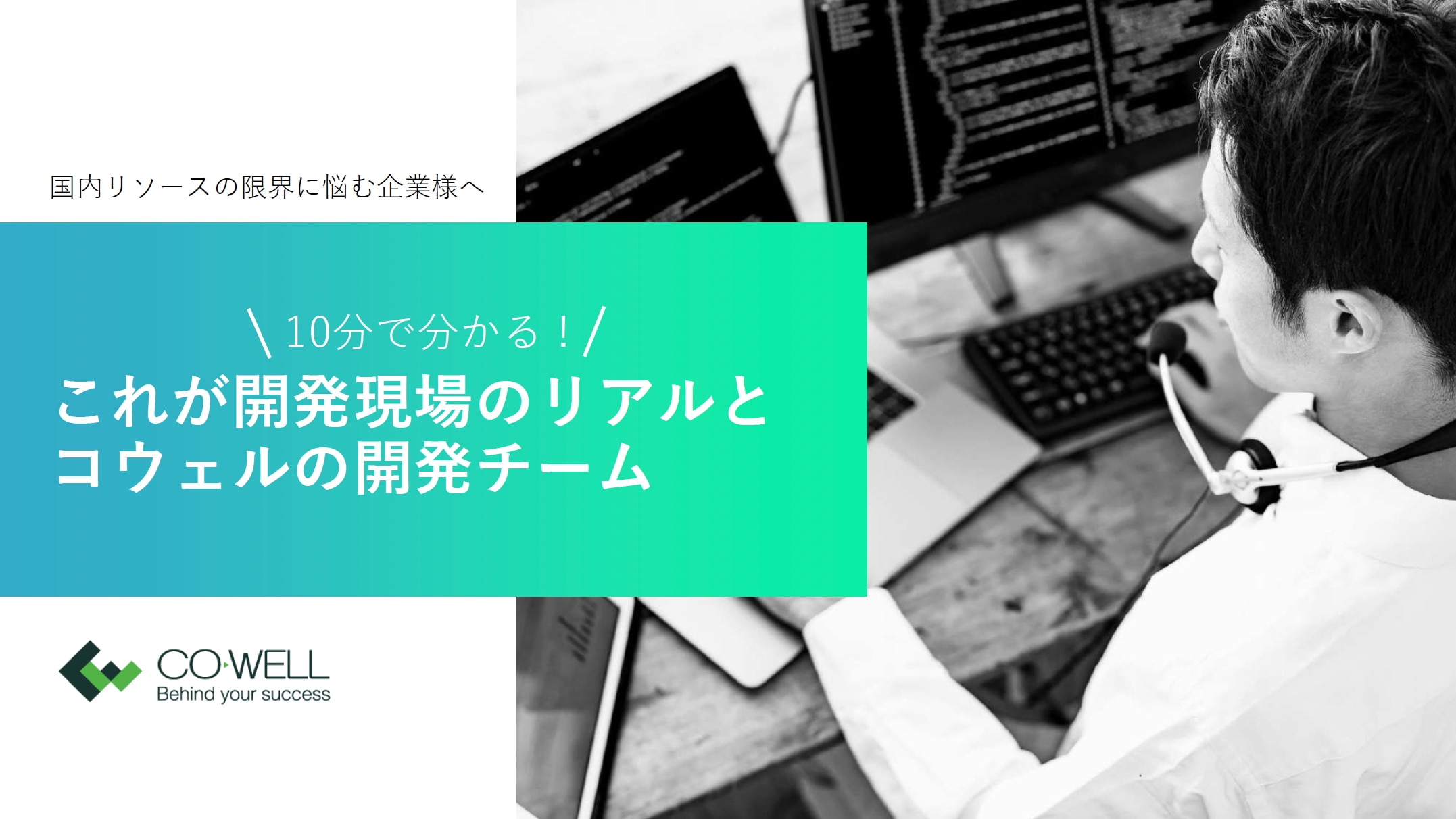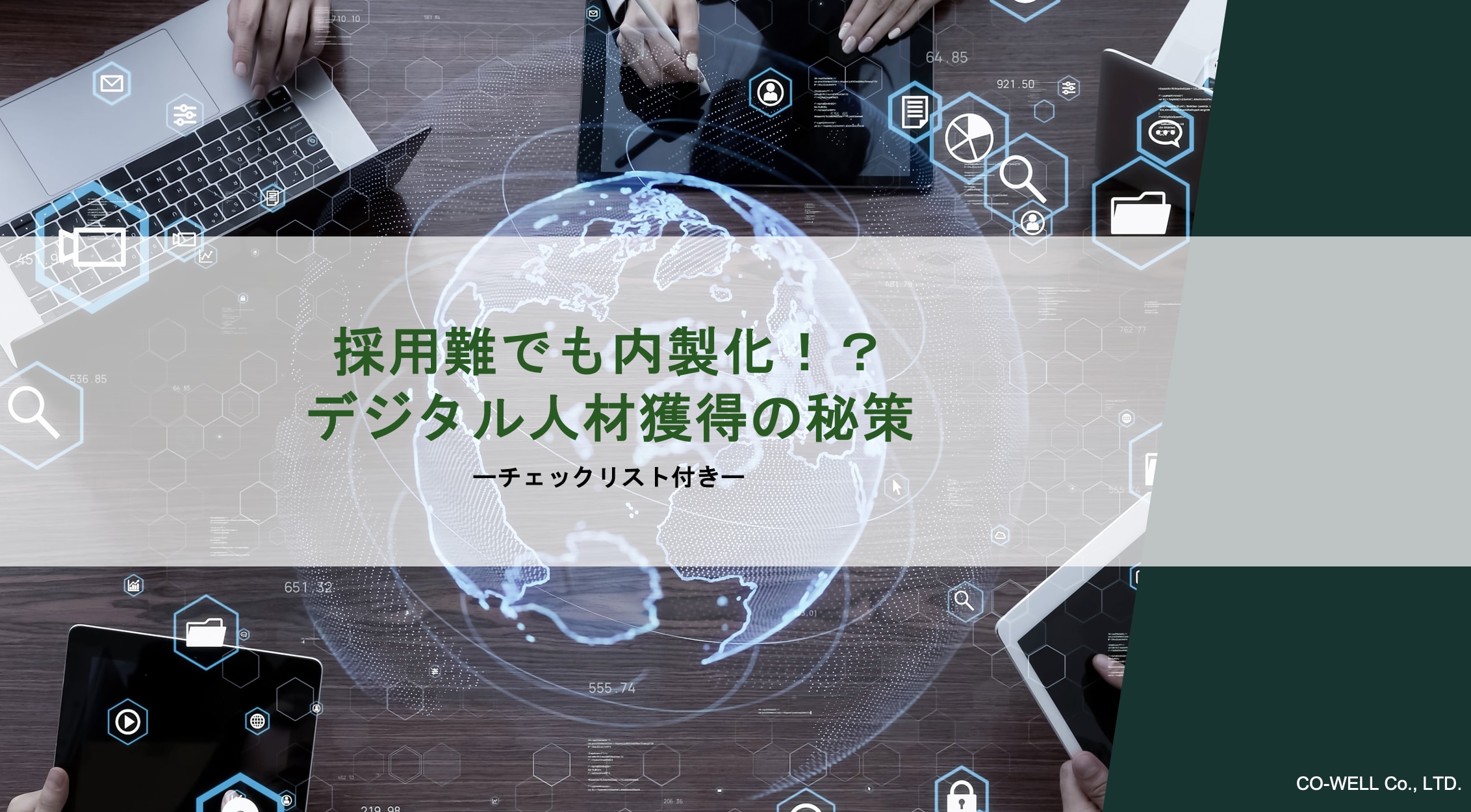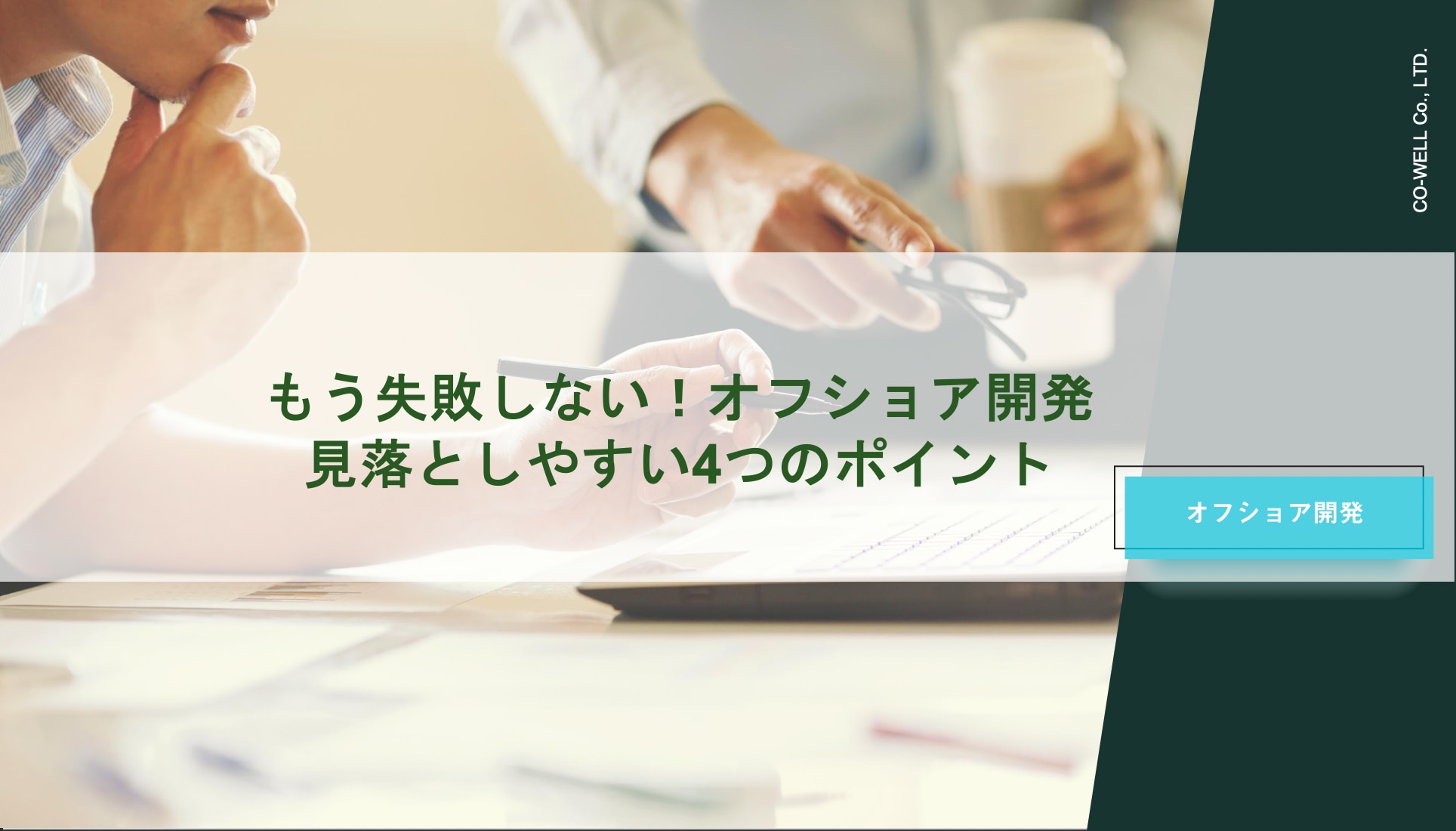WebサイトのCMS構築とは?メリットとデメリット、サイト規模別の選び方・手順と失敗しないための注意点
目次[非表示]
- 1.CMS構築とは
- 2.CMS構築のメリット
- 3.CMS構築のデメリット
- 4.CMSを構築する際にかかる費用
- 5.CMS構築における最新のトレンドと技術
- 6.CMSの選び方はサイトの目的・規模で変わる!
- 7.【種類別】CMSのメリット・デメリット
- 8.オープンソースCMSでサイトを構築する手順
- 8.1.要件定義と計画
- 8.2.サーバー・ドメインの準備
- 8.3.CMSのインストールと初期設定
- 8.4.デザインと機能のカスタマイズ
- 8.5.テストと公開
- 9.パッケージ型・クラウド型CMSでサイトを構築する手順
- 9.1.①開発会社(ベンダー)の選定
- 9.2.②サイトのコンセプトと要件の決定
- 9.3.③設計・開発・デザイン
- 9.4.④テストとコンテンツ移行
- 9.5.⑤公開と運用開始
- 10.CMS導入・リニューアルで失敗しないための注意点5つ
- 11.まとめ
- 12.オフショア開発でCMS構築もおまかせください!
本記事では、WebサイトのCMS構築に関する基本から、サイト規模に合わせた選び方、実際の構築手順や注意点までを詳しく解説します。CMSを導入することでWebサイト運用の効率化が期待できますが、その仕組みを正しく理解し、適切に導入することが重要です。
近年、多くの企業や個人がHTMLやCSSの知識に依存することなく、素早くWebサイトの情報を更新したいと考えています。そこで注目されているのがCMS構築であり、専門的なコーディング知識がなくてもシステムを活用することで運用コストを抑えつつ、柔軟なWebサイト管理が可能になります。
また、CMS導入にあたっては初期設定や移行作業などの注意点も存在するため、メリットとデメリット、さらにはサイト規模や目的に応じた適切な選択が必要です。本記事を読むことで、導入前の計画から構築後の運用まで、一連の流れを正しく把握できるようになるでしょう。
CMS構築とは
まずはCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)構築の概要を理解しましょう。CMSを利用するとHTMLなどの専門知識をあまり必要とせずにWebサイトを運用できます。
CMSとは、テキストや画像をはじめとしたWebサイト上のコンテンツを一元的に管理し、効率的に生成・編集できる仕組みを指します。従来はページの作成や更新時にHTMLやCSSのコーディングを行う必要がありましたが、CMSを導入することで専門的なプログラミング知識を必ずしも必要としなくなりました。
使用者はログイン画面から記事や画像を登録して、テンプレートをもとにWebページを作成できます。これにより、運用チームや担当者が増えても管理が容易で、リアルタイムな情報発信を行いやすくなる点が大きな魅力です。
さらに、CMSはさまざまな拡張機能やアドオンを通じてSEO対策やセキュリティ強化を実現し、企業サイトやブログ、ECサイトまで幅広く適用可能です。サイト規模や目的に応じたシステム選びが、スムーズな構築と運用の鍵となるでしょう。
CMS構築のメリット
CMSを導入することで得られる主なメリットを紹介します。
第一に、専門知識がなくてもWebサイトの更新が行いやすくなる点です。管理画面を通じて記事の編集や画像の追加を行うことで、担当者それぞれがスピーディーにコンテンツを作成できます。従来のようにコーディング作業を経ないため、修正や公開のタイミングも柔軟に調整しやすくなります。
第二に、テンプレート管理による運用コストの削減が期待できます。サイトデザインやレイアウトを一括管理し、複数のページに対して一元的に変更を加えられるため、大規模サイトでもメンテナンスにかける時間と人手を大幅に節約できます。
第三に、SEOに配慮した設計が行いやすいという点も強みです。多くのCMSは検索エンジンに適したコードを自動的に生成したり、URL構造を最適化したりする機能を備えているため、集客面でも効果を発揮します。
CMS構築のデメリット
一方でCMSには留意すべきデメリットも存在します。導入前に理解しておきましょう。
まず、初期導入時の学習コストは無視できません。システムの管理画面や設定項目に慣れるまで、ある程度の時間や工数がかかる可能性があります。操作自体は簡易化されていますが、テンプレートやプラグインの仕組みを理解するには学習が必要です。
次に、デザインやレイアウトの自由度が制限されることが考えられます。CMSはテンプレートをもとにページを生成するため、独創的なUIやUXを実現したい場合は拡張やカスタマイズが必須となり、時に追加の開発コストが発生します。
また、CMSを使用することで不要な機能が組み込まれ、動作やセキュリティ面で注意が必要になる場合もあります。機能を拡張するほどシステムが複雑化し、バージョンアップ時のトラブルやメンテナンスのしやすさに影響が及ぶ点は意識しておきましょう。
CMSを構築する際にかかる費用
CMS構築を行う場合にかかるコストの全体像を把握しておくことが大切です。
CMS導入にともなう費用には、初期導入費用と継続的な運用費用が含まれます。初期費用としては、サーバーやドメインの取得料、システムインストールやデザインカスタマイズにかかる人件費・外注費などが挙げられます。規模やカスタマイズ度合いによって変動するため、事前に明確な要件定義を行い、見積もりを取得しておきましょう。
運用費用としては、サーバー利用料やセキュリティ対策費用、必要に応じたプラグインや拡張機能の更新費などが含まれます。特に、商用パッケージ型やクラウド型CMSを選択する場合は、月額や年額のサブスクリプション費が発生するケースもあります。
長期的な視点で見た場合、CMSを導入して作業時間や人的リソースを軽減できれば、総合的にはコスト削減につながることが多いです。しかし、初期の計画や運用方針が曖昧なままだと、逆に不要な機能やサーバーコストが増加するリスクもあるため注意が必要です。
CMS構築における最新のトレンドと技術
進化し続けるCMSの世界。最新トレンドや注目技術を知ってサイト運用を有利に進めましょう。
近年はヘッドレスCMSが注目を集めており、フロントエンドとバックエンドを分割して管理する手法が増えています。この仕組みにより、モバイルアプリやIoTデバイスなど、異なるプラットフォームにも柔軟にコンテンツを配信しやすくなります。
また、MA(マーケティングオートメーション)やCRMと連携したCMSも進化を遂げています。顧客の行動データや購買履歴を参照しながらパーソナライズコンテンツを配信できるため、マーケティング戦略との組み合わせがしやすい点が特徴です。
今後はより一層、コマース機能とのシームレスな統合が進むと考えられ、大規模ECサイトでもCMSの仕組みを活用する動きが強まるでしょう。最新技術を活用することで、業務効率とユーザー体験の両方を高められます。
CMSの選び方はサイトの目的・規模で変わる!
CMSを導入する際は、サイトの目的や規模によって適切な種類を選ぶ必要があります。
小規模なブログから大規模な企業サイトまで、CMSの導入は幅広いケースで活用できます。ただし、サイトの規模や目的によって必要とされる機能やサポートは大きく異なるため、ポイントを押さえて最適解を見いだすことが大切です。
例えば、個人ブログ運営を想定している場合には、無料で利用できるオープンソースCMSが十分な機能を提供します。一方、大規模企業による複雑なワークフロー管理や高度なセキュリティ対策を必要とする場合は、サポートが充実しカスタマイズ性の高い商用パッケージ型やクラウド型CMSが向いています。
また、プロジェクトの予算や運用体制、既存システムとの連携可否なども選定時に考慮すべき重要な要素です。導入後のメンテナンスやバージョンアップにかかる負荷も含め、総合的に判断しましょう。
ブログ・小規模サイトの場合:オープンソースCMS
個人ブログや小規模なコーポレートサイト、スタートアップ企業のサービスサイトなどであれば、オープンソースCMSがおすすめです。
代表的なものにWordPressがあり、世界中のWebサイトで圧倒的なシェアを誇ります。ソースコードが無償で公開されており、ライセンス費用がかからないため、初期費用を抑えてサイトを構築できるのが最大の魅力です。
また、デザインテンプレート(テーマ)や拡張機能(プラグイン)が豊富に公開されているため、プログラミングの専門知識がなくても、比較的自由にデザインの変更や機能の追加が可能です。
ただし、サーバーの契約や設定、セキュリティ対策は自社で行う必要があるため、ある程度のWeb知識が求められます。
中〜大規模サイト・高機能なサイトの場合:パッケージ型・クラウド型CMS
数百〜数千ページに及ぶ大規模なメディアサイトや、高度な会員機能・多言語対応・外部システム連携などが必要な企業サイトには、パッケージ型CMSやクラウド型CMSが適しています。
◼︎パッケージ型CMS
商用ライセンスとして販売されている製品で、企業が必要とする機能やセキュリティ、サポート体制が充実しています。初期費用は高額になる傾向がありますが、ベンダーによる手厚いサポートを受けられるため、安心して運用できます。
代表的な製品には「Movable Type」や「a-blog cms」、「AEM」などがあります。
◼︎クラウド型(SaaS)CMS
インターネット経由でサービスを利用する形態のCMSです。サーバー管理が不要で、比較的低コストかつ短期間で導入できるのが特徴です。ただし、カスタマイズの自由度は製品によって大きく異なります。
これらのCMSは、セキュリティや安定性が高く、複数人での承認フローなど、組織的なサイト運用に必要な機能が揃っています。
【種類別】CMSのメリット・デメリット
CMSはオープンソース・パッケージ型・クラウド型など種類が多岐にわたります。それぞれの特徴を理解し、自社サイトに最適な選択をしましょう。
オープンソースCMSは導入コストが低く、コミュニティが活発なため追加機能の開発が盛んに行われています。しかし、自己責任で管理する部分が多く、トラブル発生時に専門知識が求められる場合もあります。
パッケージ型CMSは大企業や官公庁向けの大規模サイトでも安定したサポートが魅力です。カスタマイズ範囲も広い反面、初期費用が大きくなる可能性があります。
クラウド型CMSはインフラ構築やセキュリティ対策を一括してサービス提供元に任せられるため、短期導入や拡張性能を重視したい場合に適していると言えます。ただし、機能追加の際に柔軟性に限界があることは認識しておきましょう。
CMSには大きく分けて4つの種類があります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の要件に合うものを選びましょう。
種類 | メリット | デメリット |
オープンソースCMS | ・ライセンス費用が無料 ・デザインや機能のカスタマイズ性が高い ・情報が多く、問題解決しやすい | ・セキュリティ対策を自社で行う必要がある・公式なサポートがない ・アップデートなどのメンテナンスに手間がかかる |
パッケージ型CMS | ・機能が豊富で、セキュリティが高い ・ベンダーによる手厚いサポートがある ・複数人での運用に適した機能が多い | ・初期費用やライセンス費用が高額 ・ベンダーに依存しやすい(ベンダーロックイン) |
クラウド型(SaaS)CMS(例:ShareWith, Contentful) | ・サーバー管理が不要で手軽に始められる ・初期費用が安い傾向にある ・常に最新の状態で利用できる | ・カスタマイズの自由度が低い場合がある ・外部サービスへのデータ移行が難しいことがある |
独自開発(フルスクラッチ) | ・完全にオリジナルの要件やデザインを実現できる ・既存のシステムにとらわれない自由な設計が可能 | ・開発費用と期間が最もかかる ・開発を担当した会社に依存しやすい ・維持管理コストが高くなる可能性がある |
◼︎関連ページ:
オープンソースCMSでサイトを構築する手順
代表的なオープンソースCMSを利用してサイトを構築する場合の一般的なフローを紹介します。
オープンソースCMSによる構築は、低コストで自由度も高いため、幅広いサイト規模や用途に対応しやすいのが特徴です。ここでは基本的な流れを押さえることで、初めての導入でもスムーズに進められるようになります。
万全な計画を立てることが、その後の運用を円滑にするポイントです。それぞれの工程で適切な時間とリソースを確保できれば、CMS構築のメリットを最大限に引き出せるでしょう。
以下のステップを順番に進めれば、小規模なブログから中規模サイトまで、効率的かつスピーディーに構築が可能です。
ここでは、WordPressを例に、オープンソースCMSでサイトを構築する際の一般的な手順を解説します。
要件定義と計画
まず「なぜCMSを導入するのか」「どのような機能が必要か」を明確にします。現在の課題を洗い出し、必要な機能(お問い合わせフォーム、ブログ機能など)をリストアップしましょう。
まずは、サイトを通じて何を実現したいのか、どのような機能が必要かを明確化します。運営体制や更新フローなど、運用開始後のイメージも踏まえて要件を洗い出しましょう。
ターゲットユーザーの属性や目的、KPIを整理し、優先度をつけることで、過剰な機能を導入してしまうリスクを減らせます。計画段階でしっかりとゴールを設定することで、合意形成がしやすくなります。
また、必要となるコンテンツ量や運営時の担当者数を考慮し、実現可能なスケジュールを作成すると同時に、将来的な拡張を見越したサイト構造を検討しておくと安心です。
サーバー・ドメインの準備
次に、CMSを設置するためのレンタルサーバーやクラウドサーバーを手配し、ドメインを取得します。サーバー環境は利用するCMSの推奨要件を満たしているかを確認しましょう。
信頼性の高いホスティングサービスを選ぶことで、サイトの速度やセキュリティ、サポート体制においても安心できる環境を確保できます。無料・格安プランでは機能やサポートに限りがあるケースもあるため、コストだけでなく将来的な運用体制を考慮することが求められます。
ドメインは認知度やブランドイメージに大きく関わる要素のため、分かりやすさや覚えやすさを意識して選定すると良いでしょう。
Webサイトのデータを保管する「サーバー」と、インターネット上の住所となる「ドメイン」を契約します。レンタルサーバー会社によっては、WordPressの簡単インストール機能を提供している場合もあります。
CMSのインストールと初期設定
サーバーの準備が整ったら、対象となるオープンソースCMSをインストールします。WordPressなどでは、インストーラーの画面に従って必要情報を入力することで、数分で初期設定を終えることが可能です。
インストール後は、管理画面からサイトの基本情報を設定します。サイトタイトルやキャッチフレーズなどはSEOやブランディングにも関わる要素ですので、理解しやすい表現にしましょう。
あわせて、不要なプラグインやテーマの整理を行うことで、サイトの軽量化とセキュリティ向上も図れます。定期的にバージョンアップが必要になるため、更新作業のフローづくりが重要です。
デザインと機能のカスタマイズ
続いて、用意されているテーマやプラグイン、ウィジェットなどを活用してサイトの見た目や機能を整えていきます。デザインの統一感を持たせることは、ユーザーにわかりやすいサイト体験を提供するうえで欠かせません。
機能面では、問い合わせフォームやSNS連携、EC機能など、サイトの用途に応じた拡張を行いましょう。目的やユーザーの導線を考慮して設定することで、より効果的な発信を実現します。
あらかじめ用意されているテンプレートを基にするだけでなく、CSSの調整やプラグインの最適化を地道に行い、サイト全体の操作性や表示速度を向上させることが大切です。
テストと公開
サイトの構築が完了したら、公開前に必ず動作テストを行います。リンク切れの有無や表示崩れ、パフォーマンス面の問題がないかをチェックし、必要に応じて修正を加えましょう。
テスト時には、異なるブラウザやデバイスでの表示確認を行い、ユーザーが快適に閲覧・操作できるかを検証することが重要です。セキュリティ上の脆弱性を発見しやすいプラグインを用いる場合は、脆弱性診断などにも配慮すると安全性を高められます。
問題が解消されればいよいよ公開となります。公開後は定期的なバックアップや更新管理を徹底し、常に最新の状態を保つことで、トラブルのリスクを最小限に抑えることができます。
パッケージ型・クラウド型CMSでサイトを構築する手順
比較的大規模なサイトや高度なサポートが必要な場合に適したパッケージ型・クラウド型CMSによる構築フローを確認しましょう。
パッケージ型やクラウド型CMSは、サポートや機能が充実している一方で、導入やランニングコストが高くなる傾向があります。安定稼働やセキュリティを重視する企業にとっては、長期的な視点でメリットが大きい選択とも言えます。
サポートベンダーとの連携を密に行い、要件定義から公開、運用フェーズまで統一感のあるワークフローを構築しましょう。ここではおおまかな流れを解説しますが、細部はベンダーのシステム仕様や契約内容によって異なる点があるため、都度確認が必要です。
大規模サイトの場合は特にコンテンツ移行や運用フローの設計が重要で、失敗するとユーザー体験やSEO面にも影響を及ぼします。事前の計画段階で十分な検討を行っておきましょう。
①開発会社(ベンダー)の選定
初めに、実績や得意分野が自社の要件に合ったベンダーを選びます。過去の導入事例やサポート内容、費用感などを比較しながら、CMS構築の成功実績が豊富なパートナーを見極めましょう。
また、システム以外の部分(デザイン、マーケティング戦略)にも深く関わることが多いため、社内のプロジェクトチームとの連携が円滑に行えるかという点も重視する必要があります。
難易度の高い要件を提出しても、柔軟に対応できる技術力やコミュニケーション力が確保されているかをチェックすることで、構築後のトラブルを防止できます。
②サイトのコンセプトと要件の決定
次に、サイト全体のコンセプトを明らかにし、目的・目標を具体化します。既存のWebサイトがある場合は、リニューアル方針や改善ポイントを洗い出しましょう。
デザインテイストやコンテンツ量、更新頻度などを踏まえて、機能要件や対応デバイスを検討します。ユーザーが求める情報をスムーズに探せる導線を整備することが重要です。
この段階で明確になった要件をもとに、開発スケジュールや予算を策定します。赤字にならないよう、必要最小限の要件に優先順位をつけておくと導入がスムーズに進みます。
③設計・開発・デザイン
コンセプトや要件に基づき、サイトマップやワイヤーフレームを作成します。ユーザビリティを意識しながら、デザイン面と機能面の両面をバランスよく設計していきます。
並行して、CMSの管理機能や必要なプラグインなどを組み込み、セキュリティ対策も考慮しながら開発を進めましょう。大規模開発の場合はフェーズを分割し、定期的にステークホルダーとのレビューを行うことがトラブル回避につながります。
デザイン段階では、ブランドイメージの確立やユーザーの使いやすさを最優先に検討することで、集客率やコンバージョン率の向上が期待できます。
④テストとコンテンツ移行
開発が進捗したら、テスト環境で機能テストと運用テストを実施します。各機能が想定通り動くか、管理画面の操作に不具合がないかなどをチェックしましょう。
既存サイトからのリニューアルの場合は、このタイミングでコンテンツ移行作業も行います。ページ数が多いほど工数がかかるため、移行ツールの利用や作業の自動化を検討し、ミスを防ぎましょう。
テスト時にはページ表示速度やセキュリティスキャンも実施し、ユーザーにとって快適かつ安全な環境が提供できる状態へと調整を繰り返します。
⑤公開と運用開始
最終確認で問題がなければ、正式にサイトを公開します。公開後はアクセス解析の設定を行い、ユーザーの流入経路や行動を把握して、必要に応じた改善を進めましょう。
保守や運用に関するルールを文書化し、社内運用担当者やベンダーとの間できちんと役割分担を定めておくことが不可欠です。定期的なシステムアップデートやセキュリティ対策の計画も怠らないようにします。
運用開始後はデータを活用しながら、より質の高いコンテンツ提供やUIの改善を行い、CMS活用による効率的なサイト運営を実現していきましょう。
■合わせてよく読まれている資料:
【国内リソースの限界に悩む企業様へ】10分で分かる!これが開発現場のリアルとコウェルの開発チーム
CMS導入・リニューアルで失敗しないための注意点5つ
CMSの導入は、目的を見失ったり計画が不十分だったりすると失敗に終わる可能性があります。ここでは、導入を成功させるための5つのポイントを解説します。
- 導入の目的を明確にする
「更新を楽にしたい」「SEOを強化したい」など、なぜCMSを導入するのか、目的を具体的に定義しましょう。目的が明確であれば、CMS選定や要件定義の軸がぶれません。 - 運用体制を事前に決めておく
「誰が」「いつ」「どのように」コンテンツを更新・管理するのか、具体的な運用フローを事前に決めておきましょう。承認フローが必要な場合は、それに対応できるCMSを選ぶ必要があります。 - セキュリティ対策を怠らない
特にオープンソースCMSの場合、脆弱性を狙った攻撃のリスクが常に伴います。CMS本体やプラグインは常に最新の状態に保ち、パスワードを複雑にするなど、基本的なセキュリティ対策を徹底しましょう。 - データ移行の計画を立てる
既存サイトからリニューアルする場合、膨大な量のコンテンツや顧客データの移行が必要になることがあります。どのデータを移行するのか、どのような手順で行うのか、事前に綿密な計画を立てておかないと、トラブルの原因になります。 - 将来の拡張性も考慮する
現在は不要でも、将来的にEC機能や会員機能を追加したくなるかもしれません。将来の事業展開を見据え、必要な機能を柔軟に追加できる拡張性のあるCMSを選んでおくことが重要です。
まとめ
CMSを導入することで、専門知識がなくてもWebサイトの更新が容易になり、情報発信を活性化させることができます。
CMSには「オープンソース」「パッケージ型」「クラウド型」「独自開発」といった種類があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。まずは、自社のサイト規模や目的、予算、運用体制を明確にし、最適なCMSを選ぶことから始めましょう。
この記事で解説した手順や注意点を参考に、自社に合ったCMS導入を成功させてください。CMSの選定や構築に不安がある場合は、実績豊富な開発会社に相談するのも有効な選択肢です。
オフショア開発でCMS構築もおまかせください!
「なるべくコストを抑えてCMS構築したい」
「運用を外注して他の業務に集中したい」
このようなお悩みがあれば、オフショアを検討してみてはいかがでしょうか。
当社は日本とベトナム、バングラデシュに拠点を置いており、高品質なオフショア開発サービスを提供しています。
開発実績としてはWebシステムの開発や業務システム・CMS構築・越境EC開発などが豊富です。
さまざまなニーズに応えた実績もあり、経験豊富なソフトウェア開発会社です。
WordPressとAEMでのサイト構築や運用にも対応可能です。
コウェルに関する詳細資料は以下でダウンロードすることが可能ですので、何かございましたらお気軽にお問い合わせください。
■合わせてよく読まれている資料:
【国内リソースの限界に悩む企業様へ】10分で分かる!これが開発現場のリアルとコウェルの開発チーム
コウェルはお客様の課題やご検討状況に応じて、オフショア開発におけるラボ型開発やラボ型によるシステム開発をうまく進めるようご提案やご支援をいたします。
システム化・業務改善の提案からインフラ構築、システム開発、ソフトウェアテストサービス、その後の運用・保守までワンストップで対応が可能です。
ソフトウェア開発をご検討されている皆様、ぜひ一度ご相談ください。
なお、コウェルに関する詳細資料は以下でダウンロードすることが可能です。
このほか、弊社の具体的なサービスや導入事例については以下をご覧ください。
コウェルのサービスメニュー>>>
コウェルは、日本とベトナムから世界中のお客さまへ高品質なソフトウェアテスト・品質保証・オフショア開発サービスを提供しています。
コウェルの導入事例>>>
コウェルは情報通信、金融、流通・小売サービス、医療・ヘルスケアなど、さまざまな業界のお客様の導入を支援しています。